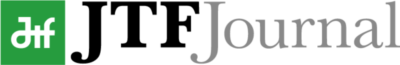ポストエディットの現場から見える三者の認識ギャップとその橋渡し~「機械翻訳ポストエディットガイドライン」公開
執筆者:一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)副会長・広報委員長/株式会社十印執行役員(法人会員)/JTF理事 石川 弘美
近年、AI翻訳技術、特に生成AIの登場により、機械翻訳の精度は飛躍的に向上しました。ニューラル機械翻訳(NMT)の登場以降、さらに生成AIの活用が進み、ニュースでもその進化が次々と報じられています。多くの企業が業務効率化を望み、AIを積極的に取り入れる動きが加速しています。
グローバル化が進む中、技術文書、マーケティング資料、法的契約書など、多様なコンテンツの翻訳需要が高まる中で、企業からは「AI翻訳を取り入れてコストを抑えたい」「スピードを上げたい」といった声が強まっています。こうした声を受け、翻訳会社の現場では、機械翻訳+人間による修正、いわゆるポストエディットを取り入れる案件が増加しています。
しかし、実際にポストエディットを導入してみると、「思っていたほど効率的ではなかった」「品質がばらつく」「想定よりも人手がかかる」といった声も少なくありません。その背景には、ポストエディットの委託組織・受託組織(翻訳会社など)・ポストエディットを行う作業者の三者の間にある“認識のずれ”が大きく影響しているように思われます。
●「AI翻訳は完璧」という誤解
まず委託組織は、AI翻訳を「完璧なツール」として過度に期待しがちです。ニュースやSNSで「人間並みの翻訳精度」と報じられ、出力の文法破綻も減少したため、品質向上、納期短縮、コスト削減を同時に実現できると信じ、従来の人間翻訳同等の成果を低価格で求めようとします。実際、市場調査でも、AI導入によるコスト削減率を30%以上見込む企業が半数を超えるというデータがあり、こうした期待は自然な流れです。
受託組織はクライアントの要求に応えるため、やむを得ず低単価・短納期の条件で案件を受託し、ポストエディットを翻訳者に発注するケースが増えています。しかし、AI翻訳の出力は、実際に作業する翻訳者の立場から見ると、「文として自然だが意味が異なる」「用語の使い方が一貫しない」「文脈の取り違え」「訳抜けの可能性で全チェックが必要」といった問題が多く、翻訳者は、AIの粗を人間翻訳に近いレベルまで磨き上げるため、文法の微妙な誤り、文脈のずれ、文化的なニュアンスの調整、専門用語の統一などに膨大な労力を注ぎます。そのため、想定以上の修正と時間がかかります。これにより、低単価では割に合わず、時間不足の不満が生じやすいのです。
委託組織はAIの「魔法」を過信し、受託組織はマージンを圧迫され、翻訳者は過酷な作業に追われる。この3者の「認識のずれ」が深刻な摩擦を生み、委託組織は「期待した品質になっていない」と不満を漏らし、受託組織は「クライアントの期待が現実離れしている」と頭を抱え、翻訳者は「報酬に見合った努力が報われない」と疲弊します。こうした不幸な結果は業界内で散見されます。
●ポストエディットの目的をどこに置くか
ポストエディットとは、機械翻訳の出力をもとに人間が修正して品質を高める工程ですが、その「品質」の定義があいまいなまま作業が進むことが多く見られます。たとえば、「出版物レベルの精度を求めるのか」「ビジネス文書として理解できればよいのか」「社内資料として意味が通じればよいのか」といった品質基準を発注時に明確にしておかなければ、ポストエディターは過剰に修正してしまい、効率性が失われます。
逆に、最小限の修正しかしなかった場合には、「品質が悪い」との不満が出ることもあります。このように、ポストエディットは単なる翻訳工程ではなく、品質・コスト・納期のバランスをいかに取るかというプロジェクトマネジメントの一環として考える必要があります。どのレベルで品質を確保するのかを、三者が事前に共有することが欠かせません。
●三者をハッピーにするためのルールづくり
こうした課題を踏まえ、一般社団法人アジア太平洋機械翻訳協会(AAMT)では、ポストエディットを業務に取り入れる際の考え方や進め方を整理した「ポストエディットガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、ポストエディットの委託組織・受託組織・ポストエディットを行う作業者それぞれの立場を踏まえ、三者が円滑に協働できるように設計されています。
委託組織に向けては、「品質とコストのバランスを意識し、事前に合意を得ること」が重視されています。機械翻訳の特性や限界を理解したうえで、目的に応じた品質レベル(たとえば「フルポストエディット」か「ライトポストエディット」か、どこまで修正するのか)を明確にし、受託組織やポストエディットを行う人と共通認識を持つことが重要です。
受託組織には、案件の特性や分野、使用するエンジンの精度、想定される修正量などを踏まえ、現実的なスケジュールと報酬体系を設計することが求められます。
また、ポストエディットを行う人自身にも、AI翻訳の特性を理解し、誤訳の傾向を把握して効率的に修正するスキルが必要です。単なる「修正者」ではなく、AIと人間の協働を最適化する「調整役」としての役割が期待されています。
ポストエディットは、単なるコスト削減の手段ではなく、AIと人間の強みを生かした新しい翻訳ワークフローの構築であるという認識が重要です。
●AI翻訳の限界を理解することから始める
AI翻訳の精度は確かに向上していますが、文脈理解や意図の読み取り、専門用語の使い分けといった点では、まだ人間の判断が欠かせません。生成AIによる翻訳でも、文としては自然に見えても、原文のニュアンスや論理構造が変わってしまうことがあります。特に契約書や技術文書など、精度が求められる分野では、人間による最終確認は不可欠です。したがって、AI翻訳を導入する際には、「どの部分をAIに任せられるか」「どの部分を人間が担うべきか」を明確にする必要があります。
ポストエディットは、その境界を見極める作業でもあります。AI翻訳の強みと弱みを理解したうえで、適材適所で活用することが、品質と効率の両立につながります。
●これからの翻訳人材に求められる視点
AIの進化とともに、翻訳者の役割も変化しています。
従来の「ゼロからの翻訳」だけでなく、「AI出力を分析し、最小限の修正で最大の品質を引き出す」スキルが求められるようになっています。一方で、ポストエディットばかりに特化してしまうと、翻訳者の表現力や文化的感性が発揮されにくくなるという懸念もあります。したがって、翻訳教育や研修の場でも、「AIと人間の協働」を前提にした新しいスキル体系を構築していく必要があるでしょう。
●ガイドラインの公開と今後の展望
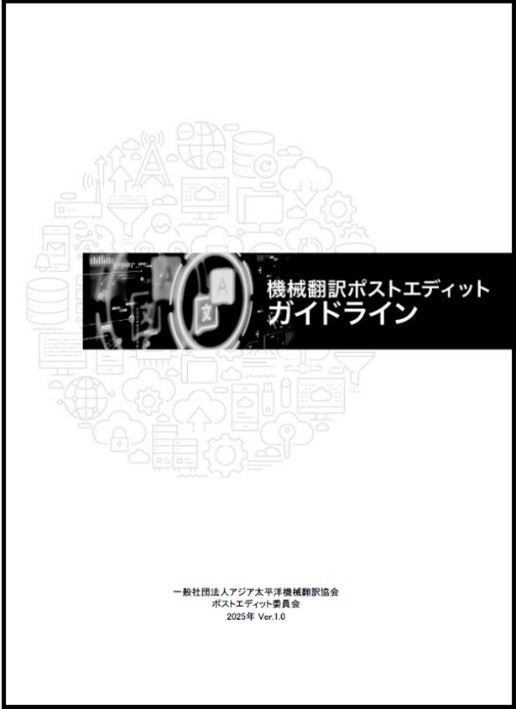
AAMTの「機械翻訳ポストエディットガイドライン」は、AAMT公式サイト(https://aamt.info/act/posteditguideline)から無料でダウンロード可能です。
ポストエディットの委託組織、受託組織、ポストエディット担当者の3者すべてが共有すべき内容となっており、ポストエディットに関わる方は参考にしていただければ幸いです。翻訳会社の方々にはクライアントへの説明の際に活用いただき、ポストエディット担当者は事前の品質合意を徹底し、業務の適正化を図ることをおすすめします。業界全体の健全な発展に寄与することを願っています。
また、2025年12月2日(火)にコングレスクエア日本橋で開催されるAAMT年次大会では、このガイドラインを策定した委員たちによるパネルディスカッションが行われます。ポストエディットの委託組織、受託組織の現場の声を踏まえた議論を通じて、より実践的な内容が展開されます。また、ポスター発表では、ポストエディットの事例発表も行われます。詳細はhttps://aamt.info/event/aamttokyo2025/をご覧ください。
AI翻訳は、翻訳業界を脅かす存在ではなく、新しい協働の形を生み出す技術です。その橋渡し役となるのがポストエディットであり、三者の立場を尊重しながら最適なバランスを探っていくことが、これからの翻訳ビジネスに求められています。
AI時代の翻訳は、単なる効率化ではなく、「人間の判断が生きるプロセスをいかに設計するか」が問われています。