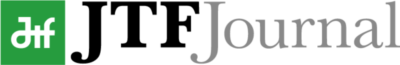1-E 翻訳教育のススメ―ひとは如何にして翻訳者になるか―
柴田 耕太郎 Shibata Kohtaro
早稲田大学仏文専修卒。岩波書店勤務、仏留学後、演劇活動。翻訳業界で40年。(株)DHC取締役、(株)アイディ代表取締役を経て、現在アイディ「英文教室」主宰。獨協大学外国語学部・東京女子大学非常勤講師。演劇・映像・出版・産業各分野に実績ある翻訳者であり、出版翻訳者を40人以上デビューさせた翻訳教育者。『英文翻訳テクニック』(ちくま新書)など著訳書十数冊。
報告者:宮下 忠雄(聴訳倶楽部〈東京・調布〉 東京・調布市生涯学習グループ(翻訳コンテンツ研究と制作)を主宰)
柴田氏の講演は、
Ⅰ 一翻訳人の歩み
Ⅱ 商品としての翻訳
Ⅲ 翻訳の編集
Ⅳ 翻訳の教育
Ⅴ 教育の実践
という5部立てで進められた。
第Ⅰ部「一翻訳人の歩み」は、柴田氏の子役時代から始まり、主にご本人の経験と回想を中心に語られたが、実はそのなかに第Ⅱ部以降の要旨が詰まっているという構成だったように思う。
講演の本論は第Ⅱ部からだ。まずは、「商品としての翻訳」、つまり職業として翻訳に従事するうえでの心構えから始まった。英文法の的確な解釈が重要であるという話として、SVOCというおなじみの用語と例文が登場したが、OとCの関係からさらに細かく読み解いてみせる。また、単複の違いで解釈が大きく変わる例文も示し、そのくらい細かい点まで正しく読み解いて初めて、商品としての翻訳を作れるのだと語った。なお、柴田氏の英文法解説は、伊藤和夫著『英文解釈教室・改訂版』を読んでご自身が感銘を受け、さらに読み深めた結果をもとに組み立てたものだという。その一部は、「研究社WEBマガジン」でも読むことができる(http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/lingua/lingua_bk01.html、現在も連載更新中)。
続いて、「良いものより悪くないもの」というキーフレーズも紹介された。その趣旨は「労働と対価」ということだった。締め切りまでの限られた時間のなか、どこまでの労力をかけ、どのくらいの報酬を受け取るかという考え方である。その説明として、たとえばAgain it came―a throatless, inhuman shriek, sharp and short, very clear and cold.という原文を取り上げた。直訳のA(略)に対し、ある翻訳本の訳B「すると、また聞こえた―声ともつかない非人間的な悲鳴だった。鋭く、短く、澄みきった冷ややかな悲鳴」と、柴田氏の訳C「また聞こえた。喉を絞ったような奇怪な叫びが、瞬時鋭く、寒々しく澄んで」が示された。Cで凝ったところは、「できるだけ短くした」ことと、頭韻を踏んでいるshriek, sharp and short, very clear and coldという原文を「瞬時鋭く、寒々しく澄んで」と、語頭のS音で再現してみたこと。プロとして「労働と対価」ということを考えれば、Bでも十分だろうが、翻訳者を志す段階ではCを目指してみるとよい。
「ニーズとシーズ」と題したパートでは、大山定一(ドイツ文学者)と吉川幸次郎(中国文学者)の翻訳論争(『洛中書問』としてまとめられている)にも言及がなされ、氏の翻訳への情熱を支えている博学ぶりがうかがわれた。この論争では、たとえばThe whole world is before me.という原文を吉川は「世界は私の前にある」と訳し、大山は「僕は前途洋々だ」と訳すという議論が展開されている。これは今なお続く議論であり、どちらが良いと断定はできないが、柴田氏の好みは大山定一調なのだという。さらには、用語も習得し、文法的に緻密に読み解いたうえで、最後には文体まで追求したい。「文体と内容は一体」であり、そこまでたどり着けば素晴らしい翻訳者になれるだろう。だが、これは人の生き方にもつながる部分でもあり、たすやく教えられるものではないとした。
第Ⅱ部のしめくくりとして提示されたのが、40年に及ぶ翻訳経験から氏が導き出した「公理と定理」だ。公理が、「翻訳とは商品である」ということ。そして、定理として以下の7点を挙げられたが、これは翻訳者にとって最も具体的に響くポイントだろうと感じた。
-
一文を短くする(目安は、井上ひさしの言う40文字)
-
掛かり方をハッキリさせる
-
読点は多用しない(読点は半拍おかれるので、意味を持ってしまう)
-
リズムある文章にする(翻訳では「音」が重要。音読をすすめたい)
-
不用意に接続詞・接続助詞を使わない(論理の流れを作るものなので、気をつけないと流れを阻害する)
-
語義は正確に使う
-
同じ言葉は続けない
ひと言でまとめるなら、「原著者が日本人だったらどう書くか」ということだ。
また、実際には、どちらとも取れる曖昧な原文もあるが、本当にどちらとも取れるのであれば、「おもしろいほうを取れ」という。なぜなら翻訳は「商品だから」である。
翻訳者にとって「営業」が大切だという指摘も、柴田氏の口から出ると、ひときわ重みがあった。その真髄は、「嘘はいけないが、薄化粧くらいはよい」ということだそうだ。
第Ⅲ部「翻訳の編集」では、編集者が聞けば耳が痛いだろうことが次々と指摘されたが、編集者が身につけるべき5つのポイントは、翻訳者としても肝に銘じるべき具体的な点だった。
-
and(andには23の意味がある)
-
カンマ(8つの意味がある)
-
記号
-
掛かり方(法則はないが通則はある)
-
日英語の誤差
この5ポイントを習得するだけで、確実に20%は読解力が上がるという。
そして、本セッションの核心である第Ⅳ部「翻訳の教育」、第Ⅴ部「教育の実践」に入ると、氏の弁にはいよいよ熱がこもってきた。翻訳に対する情熱もない人が翻訳教育をビジネスにしている現状を、氏はまず憂えている。
中学校の「英文和訳」では、文法理解が優先されるため疑似日本語が許容される。大学受験レベルの「英文解釈」になると、論理の筋を追うようになる。大学に入ると「英文講読」まで来るが、そこで終わってしまう。最終的に日本語でどうなるかまで考えなければ、真に理解したことにはならない。そのためには、日本語表現にこだわった「英文翻訳」を大学4年生の課程でやってもらいたい。柴田氏が考える望ましいカリキュラムは、文法・ノンフィクション・フィクションの三位一体の教育である。
現在、大学ではさかんに「翻訳教育」が行われるようになったが(2011年現在で、183校756講座)、翻訳教育に関しては現場のほうが先に行っている。翻訳者が学会にすり寄るのではなく、教育者が現場を知ってから抽象論に入るべきである。中野好夫は「翻訳に論などない」と言ったが、これから翻訳学というものが生まれようとしている。ぜひ形にしてほしい。
古来、日本人には訓詁癖ともいうべきものがあり、朱子学の本場である中国でさえやっていなかったような、細かい解釈が得意である。その伝統に立って細かく文法を解釈するという基本は、産業翻訳だろうと出版翻訳だろうと変わらない。たとえば、...had its effect on the little travelerという文のeffectは、「影響した」ではなく「結果を引き起こす効果、影響」であり、「効き目があった」、さらには「心に影響した」のだから「気分が変わった」と訳すこともできる。そこまで細かく読むのが翻訳である。
名文を読む、特に声に出して朗読するとよいと、ここでも音の大切さを繰り返されたが、その例として氏が披露した『金色夜叉』からの台詞の実演は、さすがに演劇もご専門という迫真の名演技だった。氏がここで演じ分けたような声色の違いを、訳文でも再現できるのが日本語の素晴らしいところだ。
また、「エラー・アナリシス」ということで紹介された英文解釈でも、接続詞forとbecauseの違い、あるいは所有格hisの付いたconversationの解釈。どれも明晰きわまりない分析的な読み方だった。この明晰な読み方こそ、氏が最後に紹介したご著書『決定版 翻訳力錬成テキストブック―英文を一点の曇りなく読み解く』(日外アソシエーツ)で詳しく解説されている読解術にほかならない。同書で氏が主張しているのは「文法力+論理力、教養力、表現力」の四位一体であり、その根幹のほとんどは「正確に読むこと」に尽きるということである。
最後に、翻訳教育が日本を救うと語り、翻訳教育の伝道師になりたい、としめくくった柴田氏。最初は、とつとつと過去話から始まった講演だったが、翻訳から翻訳教育へと話が進むほど、氏の語りからは言葉と翻訳に向けられる情熱がほとばしるように感じられた。その情熱こそ、産業翻訳・出版翻訳・映像翻訳・舞台翻訳という幅広い翻訳をこなしたうえ、翻訳会社経営というビジネスを展開し、最終的には翻訳教育という道へ柴田氏を駆り立てることになった最大のエネルギーのようだ。このセッションを聴いた参加者も、そのエネルギーをしっかりと受け取ったのではないだろうか。