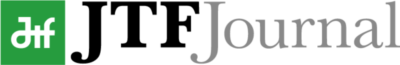第二代会長 鳥飼玖美子先生のご講演
シンポジウム
「歴代会長に聞く:日本通訳翻訳学会の過去・現在・未来―知の継承のために」
第二部:第二代会長 鳥飼玖美子先生
鳥飼先生と日本通訳翻訳学会のつながり
1990年、通訳理論研究会に初めて参加。
鳥飼先生は、大学2年生のときに同時通訳の訓練を受けそのままプロになられた。1969年東京オリンピックを契機に国際会議が急増し、ISSのような国際会議専門の会社が作られ、同時通訳者の特訓が無料で行われたので、それを受けたのが大学2年生の時であった。講師はアメリカ国務省で同時通訳訓練に関わった青山清爾氏。青山氏の口癖は”Be analytical!”(分析的であれ)であった。
その後、通訳理論研究会に継続して出席するようになり、日本通訳学会の立ち上げに関与した。初めて参加した通訳理論研究会では、10名ほどが小さな部屋で熱心に議論していた。最初の数回は余り良く理解できなかったが、セレスコビッチの名前が飛び交い、ゴンザレスの “Court Interpreting”(法廷通訳)を読もうなどという話もしていた。
当時は、勤務大学で通訳コースの導入を教授会で提案しても、「大学で通訳を教える?」「通訳に理論がある?」と失笑されるような状況であった。
通訳理論研究会が立ち上げ10年になる頃、学会にしようという話になり、2000年に日本通訳学会が発足した。近藤会長、水野事務局長という体制で、鳥飼先生は副会長に就任した。
発足時の第一回大会では、西山千氏に記念講演を依頼した。西山千氏は当時、日本翻訳家協会(JST)の会長であった。学会設立時は、新しく何かを始めるという勢いと熱意に満ち溢れていた。
近藤会長が病に倒れられたときに、会長職を受け継ぎ、鳥飼先生は2014年の9月まで会長を務められた。
鳥飼先生が努力された2つのこと
(1)海外での通訳研究を学ぶだけでなく、日本からの発信も行おうと積極的に試みた。
海外の学会での発表や学会誌への投稿、あわせて、海外での学会に参加しての報告を通訳学会誌に掲載し、海外の動向を会員に知らせると同時に、国際大会学会に参加してみようという会員の意欲喚起に努めた。
さらに、日本翻訳家協会がFIT(正式名称はFédération Internationale des Traducteursで英語名はInternational Federation of Translators)という世界規模の連盟の会員になっており、鳥飼先生もFITの理事を務めていたことから、通訳専門の学会としてFITに加盟することを考えるようになった。ただ、FITは学術団体ではなく、職能団体の性格が強いので、通訳学会は補助会員と位置付けられ、理事を出す権利は残念ながら得られなかった。
国際的な学会としては、異文化翻訳学会(IATIS)で鳥飼先生が理事を務めたことがあり、日本通訳学会会員が韓国、南アフリカ、中国、オーストラリア、アイルランドなどでの世界大会に参加し発表をしている。
(2)日本通訳学会を通訳研究に限定せず、翻訳研究も包摂することにした。
翻訳研究の発表や投稿が増えてきた背景を探ると、翻訳に関する学術研究の場が日本にはない為であることが判明し、翻訳研究にも門戸を広げたらどうかと提案した。
全会員へのアンケート調査を実施して意見を集め、理事会で議論を重ね、慎重に進めた。最終的には2008年9月総会において会員の賛同を得て翻訳研究を含めた学会に転換することが決定した。
それに合せて学会名称も「日本通訳学会(JAIS=the Japan Association for Interpretation Studies)」から「日本通訳翻訳学会(JAITS=The Japan Association for Interpreting and Translation Studies)」と変更し、学会誌の名称も『通訳研究』(The Interpretation Studies)から『通訳翻訳研究』(Interpreting and Translation Studies) と変更した。
現在、日本通訳翻訳学会の会員は500名を超えつつある。
鳥飼先生にとって残念だったこと
『黒船』『海の祭礼』など、長崎通詞を多く登場させた歴史小説家の吉村昭氏を年次大会講演にお招きしたかった。確か近藤会長の時に試みて断わられたと聞いた記憶があるが、残念であった。
鳥飼先生の通訳翻訳学会や日本における通訳についてのお考え
学会のあり方について初期の頃に議論があった。「通訳翻訳学会はあくまでも「学会」であり職能団体ではないので、通訳者の利益を擁護するAIIC(正式名称はL'Association Internationale des Interprètes de Conférenceで英語名称はThe International Association of Conference Interpretersという。1953年に設立された会議通訳者の世界的組織。会員数は3000名)のような活動は使命ではない。理論研究に専念するべきだ」という意見が多く、これまではその方針で学会が運営されてきた。
しかし、社会経済的問題が学術や教育を左右している現在の日本を見ていると、社会で現実に起こっていることに目をつぶって研究だけをしていれば良いのだろうか、という疑問も涌いてくる。
日本学術会議は、各分野の科学者が集まり政府に提言を行う内閣府直属の機関である。会員・連携会員は研究者であるが、それぞれの専門的知見に基づき、社会に対しても提言を公表している。例えば、先頃、文部科学省は、国立大学における人文社会学系学部を廃止すると発表したが、それに対し日本学術会議は、人文社会学系の研究成果はすぐに目に見えるものではないが、教育の根幹をなしていると緊急アピールを発表した。
これは学術界からの社会への貢献であり、この点を日本通訳翻訳学会もそろそろ考えてみる必要があるのではないか。
例えば、法廷通訳の問題、医療通訳の問題などは、社会と密接に繋がっており、社会的状況を無視しての研究は成立しえないし、研究成果を社会に還元することは研究者の使命ではないのか。
看過できない問題として、生命に関わる医療通訳をボランティア任せの現状を放置していて良いのか、という点がある。ボランティアの善意が、プロ通訳者の仕事の場を奪い、専門家の育成を阻害する要因になっていることをどう解決するのか。
東京オリンピックへ向けて「通訳ボランティア」が大きな流れになっているが、プロ通訳者/翻訳者の専門性が社会的に認知される又とない機会を逸することにならないか。
通訳者は今や人気の職業だとされ、少子化で冬の時代にある各大学は志願者集めに奔走している中、英語教育に通訳コースを組み込み、大学や学部の「売り」として入試広報に使っているが、だから一般的に通訳翻訳の理解が深まっているかといえば決してそうではない。未だに、外国語ができれば通訳はできる、という程度の認識が多い。
通訳翻訳は、高度な専門職であり、ボランティアに任せるべきではない。通訳翻訳が専門職として確立する為には、学部レベルだけでなく、大学院で理論と実践の研究を行い、修士号だけでなく博士の学位を授与し、研究者を育成することが肝要である。
最初に大東文化大学経済学研究科、次に立教大学(独立研究科)異文化コミュニケーション研究科が設立され、以後、日本の大学院における通訳翻訳研究が少しずつ育っているが、通訳者翻訳者養成と同時に、本格的な理論研究を深め、研究者の層を厚くすることが今後は重要になってくる。
理論研究を行う研究者を養成する為に博士後期課程を増やすこと、理論研究だけで終わるのではなく、研究成果を社会に還元することを、今後へ向けてぜひお願いしたい。
講演後の質疑応答
プロの通訳者(サイマルインターナショナル顧問 小松達也さん)からのご質問。
通訳者の社会的地位の低下を感じることがある。
扱い方も、態度もお金も変わった。
通訳はプロであるという認識が下がっているのではないかと思う。
通訳が自らを高め、通訳の地位を高めていかないと若い人が通訳になろうと思わない。かつては、通訳は 女子大の職業選択肢ではNo.1の人気だったのに。
鳥飼先生のご回答
通訳が一筋縄にはいかない複雑なコミュニケーション行為だということが理解されていないと思う。
学生にきちんと指導し、正しい理解をしてもらうよう努めよう。
学生の実態をみていると、就職先を選ぶ際に、通訳業では生活が安定しない、
と避ける傾向もある。
また、この問題は、ボランティアともかかわっている。ボランティアの通訳者・翻訳者が増えることは残念ながら、通訳翻訳の正しい理解に繋がっていない。ボランティア通訳者が増えることは、プロ通訳者の仕事を奪うことにも繋がる。素人のボランティアでもできることを、なぜプロにお金を払って頼まなければいけないのか、という考えが出てきて、プロ通訳者に対する敬意がなくなり、職業として選ぶ人間が減ってしまうのではないだろうか。
例えば、医療分野に関して言えば、医療機関や製薬会社などに通訳翻訳室を作り、通訳者翻訳者が正規職員/正社員として専門的に仕事をすることになれば、通訳や翻訳を職業の選択肢として考える若者が増えるかもしれない。
社会で通訳・翻訳を高度専門職として認知してもらうための闘いが必要。
(水野現会長コメント)
鳥飼先生の国語審議会での発言を議事録で参照すると、闘っているのが分かると思う。
(武田先生コメント)
鳥飼先生がおっしゃった「闘い」について、立教での取組みを紹介したい。
立教大学では、全学共通カリキュラムの総合科目で「翻訳・通訳と現代社会」という講義を開講している。
その大きな目的は、理解をしてくれるユーザーを育てること(将来、翻訳・通訳サービスを利用してくれる人への訴えを行う)。
具体的な授業の内容としては、現場の人に話をしてもらうことに主眼をおいている。
(1)現代社会での多文化共生の問題を認識してもらう。
(2)将来、通訳者・翻訳者になってもらう。
(3)よいユーザーになってもらう。すなわち、通訳・翻訳が簡単にできるものではないということを分かってもらう。
私自身が、かつて立教大学全学共通カリキュラムで「英語同時通訳」という科目を担当していた時には、同様の視点で授業をした。将来の通訳者を育てるという目的と同時に、将来の「理解あるユーザー、クライアント」を育てるという目的を持って指導した。これは重要な視点だと思う。