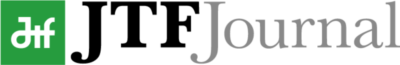文芸翻訳の作法
2014年度第5回JTF翻訳セミナー報告
文芸翻訳の作法
早稲田大学政治経済学部在学中より翻訳活動を始める。訳書に『ひとりで歩く女』ヘレン・マクロイ(創元推理文庫)、『ミッドナイト・ミートトレイン』クライヴ・バーカー(集英社)、『異邦人たちの慰め』イアン・マキューアン(早川書房)、『死の蔵書』ジョン・ダニング(ハヤカワ・ミステリ文庫)ほか多数。著書に『英和翻訳基本辞典』、『翻訳の基本』、『続・翻訳の基本』、『翻訳家の書斎-<想像力>が働く仕事場』(いずれも研究社)など、多数。ユニカレッジ講師。専修大学非常勤講師。日本文芸家協会、日本推理作家協会会員。
2014年度第5回JTF翻訳セミナー
日時●2015年2月12日(木)14:00~16:40
開催場所●剛堂会館
テーマ●文芸翻訳の作法
講 師●宮脇 孝雄(Miyawaki Takao)(翻訳家・随筆家・文芸評論家)
報告者●二木 夢子(個人翻訳者)
今回のJTFセミナー講師は、キャリア40年余の文芸翻訳家で、翻訳学校の人気講師でもある宮脇孝雄氏。本セミナー初となる文芸翻訳の講義である。ふだんは翻訳会社やクライアントの社員が中心だが、この日は多くの個人翻訳者が詰めかけた。
宮脇氏の持論は、「翻訳は頭脳労働でもあり、肉体労働でもある」。翻訳学校では、頭でどのように考えるかを教えることはできるが、身体をどう動かすかということはなかなか教えられないという。
前半はさまざまなパターンの誤訳に触れ、頭で翻訳を考え、後半は翻訳業の大先輩である二葉亭四迷(ふたばてい・しめい、1864-1909)と神西清(じんざい・きよし、1903-1957)の文章などから、身体で覚える翻訳について学んだ。
前半:頭で翻訳を考える
前半では、「次の訳文の間違いを探してみよう」と銘打って、出版済みの書籍から拾った誤訳を6点取り上げた。単純に言葉の意味を取り違えた誤訳もあったが、短い例の中に文芸翻訳ならではのエッセンスが詰め込まれていた。以下にひとつ紹介する。
例:語順を乱したことによる悪訳
原文:He was glad the doorman was occupied and didn’t see him and Mary as they were caught up in the crowd that moved toward the bottleneck at the emergency exit.
出版訳:「彼は、ドアマンが忙しく、狭い非常口へと押し寄せる群衆に自分とメアリが呑まれていくことに気づかないので、嬉しかった」
この訳は英文解釈としては間違いではないが、「非常口にたどりついた」という主題が「嬉しかった」にすり替わっていて、小説になっていない。試訳は以下のとおり。このように頭から訳すことで、緊迫感を表現できる。
He was glad
ありがたいことに
the doorman was occupied
門衛はほかのことに気を取られていて
and didn’t see him and Mary
彼とメアリを見ていなかった。
as they were caught up in the crow
そのあいだに二人は群衆に呑まれ、
that moved toward the bottleneck at the emergency exit.
非常口の隘路へと移動していった。
後半:身体で翻訳を覚える
休憩をはさんで後半は「身体」がテーマ。身体で翻訳を覚えるとは、泳げなかった人が突然泳げるようになるようなものだという。
明治39年に二葉亭四迷が書いた随筆『余が翻訳の標準』に、「苟《いやし》くも外国文を翻訳しようとするからには、必ずやその文調をも移さねばならぬ」とある。同時代の翻訳者でこのように言っている人は他にいない。この「文調を移す」ことは、特に文芸翻訳では最も重要で、「頭から順番に訳す」というのも、つまりは文調を移しているのである。実際、二葉亭によるツルゲーネフ『あいびき』は、言葉が多少古いだけで、みごとに頭から訳されている。
ある大学生用翻訳教科書には、「不要と思われる箇所を抜き出しなさい」という課題で、日本語のせりふは男言葉と女言葉の区別が語尾でわかるので前後の“he said”など(said verb)は不要であると定義されていた。これは文調を移す大切さを理解していない、間違った考え方である。特に、せりふとせりふの間にsaid verbがはさまっている場合、十数年前には省略してもよいという考え方もあったが、一呼吸入れているところを表しているので外してはならないというのが、現代の文芸翻訳の考え方である。
例:
原文:”Why, send her word to stop it,” the woman said. “Isn’t there a law?”
教科書掲載訳:「そうね、あのニオイを出すなと通知してくださいな。法律ってものがございますでしょう。」と婦人は言った。
講師試訳:「どうしろって、あのニオイを出すなと通知してくださいな。」と婦人はいった。「法律ってものがございますでしょう。」
さて音調を移しても必ずしも日本語として自然になるとは限らず、翻訳者は常に苦しんでいる。その葛藤が現れているのが、神西清が昭和13年に書いた『翻訳の生理・心理』である。ここでは、野上豊一郎の『飜譯論』に定義されている〈単色版的翻訳〉という概念についての感想が述べられている。〈単色版的翻訳〉は一言で言えば「直訳」だが、「fleeceのような雲」という表現に出遭ったとき、日本人にはぴんとこないので「わたのような雲」とするのは色を付けた訳である、fleeceと言っているのだからそのまま「フリースのような雲」とすればよい、とする論である。
神西は、この理屈はわかるとしながらも、それはあくまで生理(原理)、心理(実践)を離れての理論であると疑問を呈する。意味だけを移し替えて通じるようにするには、受け手の知性の改造、すなわち西洋化が必要である。そして、たとえ西洋化が進んだとしても、いく通りもある表現を吟味する中で、内容と形式という本来不可分なものを分けて考えるようになってしまうという。もし完全な翻訳者というものがあるとすれば、原作者とまったく同じようにものを感じる人物である。当然そんな人はいないが、作者そのものになるという誘惑にかられないかぎり、翻訳者という人間は成り立たないという。
結び
19歳ではじめて原稿料をもらい、30歳くらいのときに誘われて講師になったが、それ以来ずっと、翻訳は教えられるものなのかと考え続けている。理論は教えられても、身体にリズムを叩き込むことはできない。出版翻訳を志す人には、あれもこれもと思うのではなくジャンルを絞り、とにかく本を読んでもらいたい。すでに数百万冊の本が世に出ているので、読まなければならない本はジャンルごとに2~300冊はある。まず本を読むこと。読めば身体にリズムが叩き込まれる。
感想
前半の誤訳探しはパズルのようで楽しく、訳し下ろしのテクニックにも目から鱗が落ちたが、後半では偉大な先人たちの問いかけが胸に突きささった。二葉亭四迷は、翻訳のリズムを移すために句読点の数まで合わせようとした。神西清は、原著者になりきる誘惑に憑かれないかぎり翻訳者という人間は成り立たないと悩みぬいた。私が日々従事する実務翻訳では、文書の種類など諸条件により必ずしも文調を移すことが重視されるわけではないが、「何を移すべきか」というコアの部分と、残念ながら移せなかった部分は、案件ごとに必ず存在する。その吟味を常に忘れず、苦しみながら翻訳と向き合わなければならない。そう気持ちを新たにさせられる講義であった。