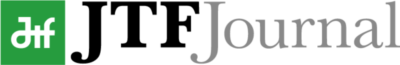6-3 大学における通訳者養成:理論と実践
武田 珂代子 Kayoko Takeda
立教大学異文化コミュニケーション学部教授。会議・法務通訳者、実務翻訳者としての長年の経験にもとづき、通訳翻訳の歴史や教育、社会文化的側面に関する研究に取り組む。2016年度立教大学・大学院で通訳者・翻訳者養成プログラムを立ち上げ、指導。日本通訳翻訳学会副会長。2011年までミドルベリー国際大学モントレー校(MIIS)翻訳通訳大学院日本語科主任。米国時代に外務省、カナダ政府の通訳者養成、通訳資格試験に従事。元カリフォルニア州認定法廷通訳者。MIISで翻訳通訳修士号、ロビラ・イ・ビルジリ大学で翻通訳・異文化間研究博士号を取得。著書に『東京裁判における通訳』、訳書に『翻訳理論の探求』(A・ピム著)などのほか、論文多数。
報告者:中林 夕子(通訳者)
日本における通訳者養成の背景や提供プログラムは、欧米・アジア主要国における実践と異なる。相違点に関する歴史的背景の説明に加え、日本の通訳者養成プログラムの概要、また高等教育機関における通訳教育の現状と課題について、立教大学の例を含めて説明したい。
現在、通訳者養成プログラムでは「言語習得」ではなく、通訳スキルを教えるのが当たり前とされているが、このアプローチが始まったのは20世紀以降である。重要な節目としては、1919年のパリ講和会議があり、この会議をきっかけに専門職としての会議通訳者が配置されることになった。当時は、話者がスピーチ全体(30分以上のこともあった)を話し、そのあと通訳者が演台で逐次通訳を提供するという形式が主であったため、必然的に通訳者には、ノートテイキングやパブリックスピーキングの能力などが求められた。また外交や国際関係の場で仕事をするため、高学歴かつ高い教養が求められた。それが通訳者養成法に現在でも反映されている。
以降、通訳者のニーズが高まるにつれて、1920年代にジュネーブ大学がノートテイキングを中心とする逐次通訳クラスを提供し始める。1928年には、国際労働機関での総会(ILO)とコミンテルン大会で同時通訳が試験的に行われ、その後ニュルンベルク裁判で同時通訳が本格的に実施されたことを皮切りに、同時通訳の教育も開始された。1953年には、会議通訳者が集まって国際会議通訳者協会(AIIC)が創設され、スクールポリシーとして、「大学院での教育、現場と同様の通訳ブースを使用、卒業試験が必要、講師は現役の通訳者であるべき」など、様々な要件を設定された。こうしてAIICが認定する“ベストプラクティス”が主にヨーロッパの高等教育機関での通訳者養成プログラムの基準として認識されるようになった。
通訳者養成プログラムの実践は、英語とフランス語の二言語が公用語であるため日常的に会議通訳が必要となるカナダや、コミュニティ通訳に力をいれるオーストラリア、大学が通訳エージェンシーの機能も果たす韓国、国連と政府の協力で会議通訳者養成が始まった中国、通訳国家試験の作成や評価基準の設定に複数の大学が関与する台湾など、国によって様々である。
日本の場合は、終戦からわずか11日後に通訳募集の案内がでるなど、GHQからの要望に応じてほぼ毎日通訳・翻訳の募集があった。養成については、外務省や警視庁などによるプログラムがあった。1950年のスイスMRA大会や、1955年の原水禁世界大会などで同時通訳の実践が始まり、高度経済成長とともに通訳の需要が激増したことで、通訳エージェンシーが誕生し、その後エージェンシーがスクールを併設し、通訳者養成クラスを一般に提供し始めた。
このようなスクールと大学院での通訳者養成プログラムにはそれぞれ利点と課題がある。大学院通訳プログラムの利点は、厳しい選抜条件(立教大学では、通常の大学院入試に加え、英検1級・TOEFL 100点・IELTS7.0の資格要件)を設けているため、語学ではなく通訳スキルに焦点を置いた通訳者養成が行える。また、諸外国では大学院で通訳者を養成することが標準的であるため、外国の教育機関との提携、情報共有や交流が可能。また大学院は研究の場でもあるため、研究の成果を教育に生かせる相乗効果も得られ、さらに専門職として養成しているため、社会的認知の向上にも貢献できる。また、国連機関や多国籍企業ではインハウス通訳のニーズがあるが、海外派遣のための査証発行には専門職(修士号)の資格が必要となり、その条件にも対応が可能。一方、課題については、日本では通訳者の派遣はエージェンシー主体であるため、大学で訓練を受けた学生の場合、市場とのつながりが十分ではない。また教員の確保についても、博士号、研究業績および通訳実務経験を兼ね備える教員が限定されるため、確保が難しいのが現状。
立教大学においては、学部長の積極的な支援のもと、通訳教育プログラムを学部と大学院で提供。さらに「立教コミュニティ翻訳・通訳(RiCoLaS)」を立ち上げ、教室内で学習したスキルを実際のプロジェクトで活用できるようにサービスラーニングシステムを提供し、クライアントのフィードバックなどをもとにした振り返りを学生が行う取り組みを開始。今後も現場、クライアントのニーズに即したサービスプログラムを提供していきたい。
質疑応答
質問:本日お話し頂いた日本国内の通訳養成の経緯・実践については、言語は英語を前提としているものか?
回答:紹介したのは英語。ただ、中国語の通訳者養成もISSで実施されている。
質問:法廷通訳に関して、インドネシア語通訳者の誤訳問題が取り沙汰されたが、裁判所で教育システムが確立されていないのが問題だと思う。
回答:法廷通訳者の認定試験がないのが問題。今後認定制度が構築されるべきだと考えるが、誰が作るのか、どこが運営するのかなどの問題が生じる。通訳者としての職務倫理に関するトレーニングなど、短期的にできることはあるはず。また裁判所でも人選プロセスをきちんとするべきと考える。通訳者としては、自分の能力を超える仕事を受けてはならない。参考になるのは、米国における少数言語の司法通訳認定試験。通訳技術の試験は実施していないが、英語と対象言語の語学試験を行う。試験には、法律的や司法制度の内容を含むため、司法の場で言語が操れるかの一つの物差しになる。
質問:現在、民間の通訳学校に通っているが、大学院の通訳育成プログラムにも興味がある。民間と大学院の通訳プログラムの違いは?
回答:民間のスクールの経験がないので正確には言えないが、大学院では修士論文、通訳理論や通訳学の科目がある。理論や実証研究の成果を学ぶことで、自分がしていること(通訳)を系統的に説明できる力(メタ認知能力)がつく。また門を絞っているので、履修者の人数が少ない(現在の学生数は1クラス3名)。
参加する養成学校運営者からの意見:民間のスクールでは訳出の訓練とスキルアップが主体であるが、大学院では理論を教える点が大きな違い。また、民間では企業のニーズが把握しやすいため、現場のニーズに沿ったプログラムを組むことができる。
質問:海外大学院の通訳養成プログラムでは、日本語と欧州言語のペアを提供していない。
回答:一部している。その年度の入学者の言語ペアによって提供するクラスを調整するので、問い合わせるのも一つの案。通訳入門クラスで行われるActive Listeningなどは言語に関係なく受講できる。言語に特化した通訳訓練はチューター制度で指導という形式で実施している大学もある。
質問:ノートテイキングの技術は独学で習得できるか?
回答:ノートテイキングは手段であって目的ではないので、訳出がよければそれでいい。実証研究の論文などを読んでいろいろ方法を模索して、自分に合うやり方を見つけるというのも良い。グループで練習しそれぞれの実際のメモを共有することで、他の人から学ぶこともできる。
質問:立教大学での通訳養成プログラムでは、同時、逐次、ウィスパ通訳はどのように教えているか?
回答:基本的に逐次通訳を習得したのちに同時通訳に移行する。ウィスパのみの授業を行うことはないが、現場では必要な形式であるため、RiCoLaSでは簡易通訳機器を購入してラーニングの機会に役立てている。ヨーロッパでは逐次通訳からスタートさせることに異論もあるが、立教では逐次から始めている。