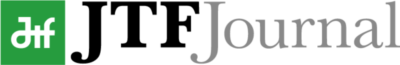iPS細胞を用いたパーキンソン病治療
10/26 Track1 10:00-11:30
髙橋 淳 Takahashi Jun
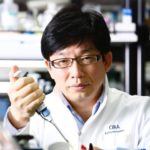
京都大学iPS細胞研究所
臨床応用研究部門 教授 博士(医学)
京都大学iPS細胞研究所 臨床応用研究部門 神経再生研究分野 教授。1986年 京都大学医学部卒業、同大学同学部附属病院脳神経外科で研修医を経て、米国ソーク研究所留学。帰国後は京都大学医学部に戻り、脳神経外科助手、講師、京都大学再生医科学研究所生体修復応用分野准教授、2012年より現職。再生医療を用いた神経難病の治療開発に力を注ぎ、iPS細胞を用いたパーキンソン病治療に取り組んでいる。
報告者:笠川 梢(フリーランス翻訳者)
再生とiPS細胞
プラナリアを例にして、治るとは何か、再生とは何かを考えてみよう。プラナリアは体長約1cm。下等生物だが、どこを切り刻んでも新たに体ができる。つまり傷が治り、再生される。プラナリア以外でも自分の体を自分の細胞で治すことが再生。そもそも治癒とは自己修復なのだが、高等生物は基本的に自己修復できない。例外として皮膚など体の表面では新しい細胞が日々生まれている。でも、その部位は限られている。そして、パーキンソン病で問題となる神経は再生しない。
生物は進化と共に再生能力を失ってきたが、これを可能としたのがiPS細胞(人工多能性幹細胞:Induced Pluripotent Stem Cells)である。ジョン・ガードン博士と山中伸弥博士はこの研究で2012年にノーベル生理学・医学賞を共同受賞した。それまでの研究から、細胞の性質は遺伝子によって決められていることはわかっていた。核の中にDNAが入っていて、それぞれのDNAには皮膚なら皮膚の作り方など固有の設計図(遺伝情報)が入っている。ただ、成熟した細胞の中に他の細胞の遺伝子はなくなっているのかどうかについて、当時はわかっていなかった。
ガードン博士は、未受精卵の核を取り出し、代わりに腸の細胞の核を入れる実験を行った。その結果、オタマジャクシ(カエル)が生まれ、腸の細胞にすべての遺伝子が残っていることがわかった。つまり、他の情報も鍵がかかって読めなくなっているだけであって、残っていたのだ。そして、鍵を外してやれば(初期化=reprogramming)、自己修復の可能性があるとわかった。山中先生が行ったことはこの初期化である。2006年にマウス、2007年にヒトの皮膚の細胞からiPS細胞が作製された。iPS細胞には自己複製能(ドンドン増える)と多能性(あらゆる細胞になる)の2つの性質がある。ES細胞もその約10年前に作製されていて、多能性を持っている。ただ、ES細胞は受精卵の内部細胞塊を取り出して作るところがiPS細胞とは異なる。
iPS細胞をパーキンソン病に
パーキンソン病とは、中脳黒質のドパミン神経細胞が進行性に脱落する疾患。手足の震え、こわばり、運動低下が生じる。50歳以降に発症することが多く、日本には約16万人の患者がいる。この病気でドパミン神経細胞が減ると脳内のドパミン量が少なくなる。ドパミンは直接飲んでも脳に届かないが、L-ドパという薬剤があり、これがドパミンになる。ただし、L-ドパが効くためにはドパミン神経が必要。ドパミン神経がなくなってくるとL-ドパの効かない時間が増えるのが課題となっている。
治療の基本は薬だが、電気的刺激や遺伝子治療もあり、治療方法は変わってきている。ただ、いずれも今ある細胞をいかにやりくりするかという治療。体内にある細胞を変化させるのではなく、細胞を新たに補う治療が細胞移植である。パーキンソン病においては、細胞の減少が根本原因なのでこれを補えばよい。ドパミン細胞を移植すればドパミン量が増える。今までは薬やリハビリ、医療機器が直接治療していたが、細胞を中心とした新しい治療戦略が生まれている。
1987年、スウェーデンのルンド大学ではヒト胎児の細胞を世界で初めてパーキンソン病患者に移植し、その後、アメリカなどでこの胎児細胞移植が約400例行われている。中軽症例で改善がみられ、10年以上効果が続く例がある一方で、細胞の採取や倫理面に課題がある。
そこで注目されたのが幹細胞。当時、京大の脳外科医だった登壇者は故笹井芳樹先生からの電話がきっかけで研究の道に進むようになった。最初の課題は、どうやってドパミン神経細胞を作るか。ほしいのはドパミン細胞だけ。数ある神経の中でドパミン細胞だけを作り、腫瘍は作らないようにするにはどうすればよいか。そのために開発したのがセルソーティング(Cell sorting)という技術。まず、ヒトiPS細胞を分化誘導してドパミン神経前駆細胞が20~50%含まれた神経幹細胞を作る。次に、コリン(Corin)という中脳floor plateの特異的表面マーカーを用いて、ドパミン神経前駆細胞だけを光らせて、選別するセルソーティング技術を開発した(2014年、マウスでのドパミン神経前駆細胞の製造法開発)。
次に課題となったのは、霊長類でも機能するかどうかだった。そこでカニクイザルを小さなヒトと見立てて、臨床試験のシミュレーションを行った。実験ではカニクイザルを薬でパーキンソン病にして細胞を移植。サル用のUPDRS(パーキンソン病総合評価尺度)を作成し、測定した。また、ビデオによる行動解析の方法も開発(画面上で動いたピクセル数の変化で症状の程度を比較)。どちらにおいても有効性が認められた。移植した細胞による改善であることはPETでドパミンが合成されていることで確認した。移植した細胞が脳内で増えて、腫瘍を作るのではないかという懸念があったのでこれについてもMRIなどで調べた。2年間観察した結果、腫瘍は作られず、安全性が確かめられた。さらに、ドパミン細胞が生着していることも脳の染色により確かめた。一般的に患者さんでは、報告により差はあるが、ドパミン細胞が約10万個生着すれば症状が改善する。この実験では約13万個生着していた。
免疫反応についても確認した。この治療では他人のiPS細胞を移植する。同じHLA(免疫のタイプ)の型を持つ患者に移植すると免疫拒絶反応の低下が期待できる。最頻度の免疫型を持つiPS細胞では、人口の約17%をカバーすることができる。そこで、免疫型が合っている細胞と合っていない細胞をカニクイザルに移植した。その結果、型が合っている場合は免疫反応が抑えられ、ドパミン神経の生着が良好であることを確認した。
研究では早期から企業と連携してきた。2014年から大日本住友製薬と共同で研究することにより、社会の役に立つのかどうなのかという企業目線を取り入れている。PMDA(医薬品医療機器総合機構)との戦略相談は2015年以降、22回行っている。京都大学医学部附属病院との協力体制も構築した。
基礎研究と実用化の間には「死の谷」と呼ばれるギャップがある。これを克服し、いち早く医療の形で社会に還元することが課題となっている。死の谷を越えるためにはここまで述べてきた科学的根拠に基づく治療法の開発、臨床株を用いた十分な非臨床研究の実施、研究早期からの企業や関係省庁との連携が重要である。国からのサポート(再生医療の実現化プロジェクトなど)も大変重要である。
パーキンソン病患者に移植
治験では、単施設(京大病院)、非盲検、非対照で患者7例に対して、術前と比べて症状がよくなったかどうかなどを調べる。健常人ドナーから樹立したiPS細胞をドパミン神経前駆細胞にする。それを病院で患者に移植。あらかじめMRIで注入部位を決め、頭蓋骨に穴を開けて針を刺し(定位的脳手術)、左右それぞれ約240万個、合計約500万個の細胞を移植する。術後はタクロリムス(免疫抑制剤)を約1年間投与し、全体で2年間観察する。主要評価項目は安全性(有害事象、移植片増大の有無)。副次的評価項目は有効性(MDS-UPDRSなど)。PET検査でも安全性と有効性を評価する。
質疑応答
Q1 患者としては何ができるか。
A1 幸いパーキンソン病には患者会がある。患者は意見をはっきり言うこと。研究の方向が患者のニーズからずれる可能性がないとはいえない。
Q2 iPS細胞で人間ができる可能性は。
A2 マウスでは精子や卵子ができているため、ヒトでも可能性はある。ただし、倫理的問題をクリアしなければならない。
Q3 治験の対象者に重度パーキンソン病患者が含まれていないが、重度患者こそ治療法を求めているのではないのか。
A3 重症患者ではドパミンに対する反応性が失われているので、この治療で重度患者の症状を改善することは難しい。将来的には、早期にこの治療を行いパーキンソン病が悪化しない環境を作りたい。そのためには若いうちから細胞バンクに細胞を残し、自家移植のための準備をしておく方法も考えられる。