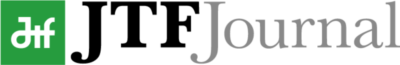翻訳者/通訳者の役割
2012年度JTF定時社員総会基調講演
翻訳者/通訳者の役割
鳥飼 玖美子
立教大学特任教授、国立国語研究所客員教授

2012年度JTF定時社員総会基調講演
2012年6月7日(木)15:00~16:10
開催場所●ホテル銀座ラフィナート7階
テーマ●「翻訳者/通訳者の役割」
講師●鳥飼 玖美子 立教大学特任教授、国立国語研究所客員教授
報告者●新江 裕吾 個人翻訳者
撮影者●森脇 誠
通訳・翻訳研究は、海外では早くから始まっている。通訳学に関しては、第二次大戦後のニュルンベルグ裁判で導入された同時通訳について、心理学、認知科学、人工頭脳などの研究者たちの関心が喚起され、さまざまな研究が始まったのがその端緒であった。翻訳については、それこそ紀元前から、直訳と意訳、忠実訳と自由訳などの問題、2言語間での単語の等価はありえるのか、といったさまざまな議論がなされてきた。1970年代頃から本格的な研究が進み、訳出物の検討から、翻訳のプロセス分析へと多様な研究が行われ、最近は訳出行為をする人間についての関心が深まっている。これは通訳翻訳分野の多様化が要因であろう。
たとえば翻訳では、かつては文学翻訳が主流だったが、今では実務翻訳、技術翻訳が大半を占めている。そして映像翻訳のような新しい分野では、プロではなくファンが作る字幕の「ファンサブ」が大きな存在になっている。そこで、素人とプロの違いは何か、という問題も研究対象になってきている。通訳でも、以前は会議通訳者、同時通訳者が主流だとされてきたが、今は「コミュニティ通訳」と総称される対話通訳が世界的に注目されている。コミュニティ通訳では、たとえば医療通訳といった、生命が関わるような問題を扱わなくてはならない通訳を、子供やボランテイアが行うことが多いし、司法通訳、法廷通訳では研修の充実や資格制度の実現が課題となっている。
それでは、どういう人がプロの資格があるといえるのか。たとえば、私が研究対象とした、日本の同時通訳パイオニアの5名は、誰も本格的な研修や訓練などは受けていない。だからといって、この人たちが素人だ、とは誰も言わない。ではこの人たちはどのようにしてプロになったのか、何が素人と違い、いつから素人との違いが出てきたのか、というのは案外難しい問題である。プロフェッショナリズムとは何か、専門職の人間はその業界で必要な「規範」(norms)をどうやって身に着けるのか、という規範研究が、現在の通訳・翻訳研究で大きなテーマになっている。
規範については、1995年にGideon Toury が著書で論じ、2000年にはAndrew Chestermanが分析している。専門職としての「プロフェッショナル規範」は「期待規範」(expectancy norms)の影響を強く受ける。この期待規範は、クライアントやエージェントから通訳者翻訳者に対して寄せられる期待のことだ。たとえば、通訳した内容を外部に漏らさないというのは、通訳者に共通の倫理であるだろうが、これはクライアントが強く望むことであり、エージェントもきちんと押さえていることであるから、業界の規範であると言えるだろう。
しかしながら、個々の翻訳者・通訳者が内在化している規範というのは、どこで育まれているのか、そしてそれは実際の仕事においてどれだけ意識されているのか、現実の訳出行為にどの程度の影響を持っているのか、ということはなかなか分からない。カナダのJean-Marc Gouanvicという研究者は規範に関する論文で「翻訳者は、自分の内部の何か主観的なものに従い、その都度判断して翻訳しており、規範だけでは翻訳者の訳出行為を説明できない場合が多い」と述べている。翻訳者・通訳者の頭の中を解明しようと、"TAP=think aloud protocol" という、頭の中で考えていることをマイクの前でしゃべってもらうという研究方法を応用し、翻訳者が訳出中に考えていることを解明しようと試みた研究者もいたが、うまくいかなかった。近頃はキーボード・ストロークをデジタルに記録するソフトを使用しての分析も出てきている。
最近では社会学の知見を応用することが盛んになってきており、その1つとして、フランスの社会学者Pierre Bourdieuの"ハビトウス(habitus)"という概念を応用して、翻訳者・通訳者の実践を解明しようという研究が出てきている。私は、このハビトウスを研究する手段として”oral history”という歴史学の手法を応用した。oral history では、歴史に残らないであろう、無名の人々の生きざまをインタビューして録音する”life story interview”という手法がとられる。この研究手法は、自らの声を発することが許されない通訳者に最適だと感じた。
そこで、貴重な資料として残しておくべきだと思われた同時通訳パイオニア5名の方たち、相馬雪香さん、西山千さん、村松増美さん、國弘正雄さん、小松達也さんの語りを記録し、なぜ通訳者になったのか、どういう思いで通訳をしたのか、ということを分析し、通訳者の役割を浮き彫りにしようと考えた。この方たちは日本の通訳界のパイオニアで、訓練らしきものも受けていない。通訳を始めた時には業界もなく、後から自分たちで作っていった。このため、日本における通訳ハビトウスというのは、この方たちが少しずつ形成していったともいえる。ところがハビトウスを探るというのは至難である。そもそも通訳規範をどのように身に着けたのかさえ、本人もよくわからない。5名の多くが通訳者は黒衣であり透明な存在で、目立ってはいけない裏方であると語ったが、そういいながらも、実際の通訳では透明ではない場合があり、その場その場のコンテクストをふまえて臨機応変に通訳をしている状況が判明した。
結論を申し上げると、通訳者というのは、規範を自分なりに意識しながらも、実際の通訳行為にあたっては状況に応じて独自の判断を行って訳語を選択している。これは通訳という営為が即時性を問われるということもあるかもしれないが、同じことは時間的余裕がある翻訳者にも言える。「訳す」という実践には自律した人間が関わるとも考えられる。コミュニケーションの場において、通訳者は、見えない存在どころか、話し手と聞き手の間に入る3人目の存在として、「今、ここ」の会話に極めて能動的に参与し仲介者としての役割を果たしている。黒衣と言われることの多い通訳者あるいは翻訳者が、その場のコンテクストを見極めながら自律的に柔軟な判断をする。それこそが機械ではできない、人間の翻訳者通訳者の役割ではないだろうか。